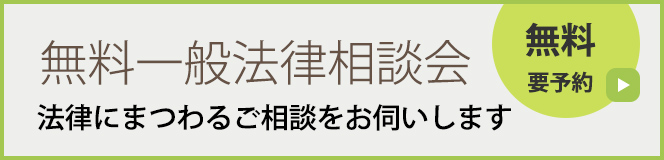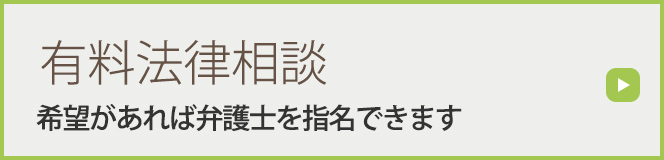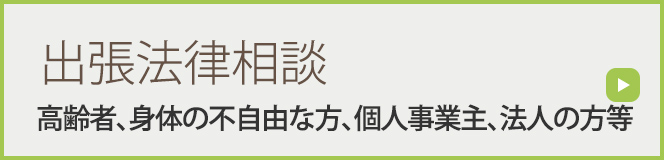遺留分について
遺留分とは、一定の相続人が、法律上取得することを認められている相続財産の割合のことをいいます。すなわち、被相続人(亡くなった人)の意思によっても処分できない相続人の取り分です。相続財産がない場合でも生前贈与があれば遺留分が問題になることがあります。遺留分権利者が自分の取り分を主張して請求することを、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。この遺留分減殺請求は、一定の期間内に行使する必要があります。
では、相続分と遺留分はどのように違うのか、具体例を見てみましょう。
<具体例1(相続分)>
被相続人(亡くなった人):A
相続人:B(Aの長男)、C(Aの二男)
相続財産:現金1000万円
Aの遺言:なし
→Aの遺言はありませんので、Aの相続財産のうち、Bの法定相続分が500万円、Cの法定相続分が500万円となります。
<具体例2(遺留分)>
被相続人(亡くなった人):A
相続人:B(Aの長男)、C(Aの二男)
相続財産:現金1000万円
Aの遺言:「相続財産をすべてBに相続させる」
→Aの遺言書によって、Bが現金1000万円を相続します。
ただ、Cには、法律上取得を認められている相続財産の割合があり、この割合が遺留分(Cの場合は4分の1)です。
Aの遺言は、Cの遺留分である4分の1以上の相続財産をBに相続させるものですので、Cの遺留分を侵害しているといえます。そこで、Cは、相続財産の4分の1にあたる250万円の限度で、Bに対し、返還するよう請求〔遺留分(いりゆうぶん)減殺(げんさい)請求〕することができます。
このように、遺留分は、遺言者Aの意思でも処分できないCの最低限の取り分といえます。
Q 誰が遺留分権利者となりますか。また、その遺留分の計算はどうなりますか。
A 遺留分権利者は、原則として兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)です。
遺留分の計算は、まず、相続財産に対する遺留分の割合(全体の遺留分)を算定します。この割合は、直系尊属のみが相続人であるときは3分の1、その他の場合には2分の1です。
次に、相続人ごとの遺留分を算定します。相続人ごとの遺留分は、全体の遺留分を法定相続分に従って配分します。
<具体例3>におけるB、Dの遺留分をそれぞれ算定してみましょう。
<具体例3(遺留分の算定)>
被相続人(亡くなった人):A
相続人:B(Aの妻)、C(Aの長男)、D(Aの二男)
相続財産:現金1000万円
Aの遺言:「相続財産をすべてCに相続させる」
→まず、相続財産に対する遺留分は、「直系尊属のみが相続人である場合以外の場合」であるため、2分の1(500万円)です。
次に、全体の遺留分(500万円)を法定相続分に従って配分し、B、Dそれぞれの遺留分を算定します。
BはAの妻であり法定相続分は2分の1ですので、500万円の2分の1である250万円がBの遺留分となります。
DはAの子であり、具体例3での法定相続分は4分の1ですので、500万円の4分の1である125万円がDの遺留分となります。
したがって、Bは250万円、Dは125万円の限度で、Cに対し、返還の請求(遺留分減殺請求)をすることができます。
Q 遺留分減殺請求はどのように行えばいいですか。
A 遺留分減殺請求は、遺留分減殺請求をする旨の相手方に対する意思表示をもってします。この場合、後日、意思表示をしたことについて証明するために、内容証明郵便を用いるのが一般的です。
Q 遺留分減殺請求はいつまでにする必要がありますか。
A 遺留分減殺請求は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは、することができなくなりますので、それまでにする必要があります。